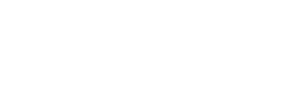
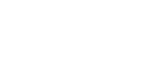

不動産を所有している場合、駐車場や駐輪場として活用するケースが散見されます。駐車場や駐輪場を運営すれば、利用料を売上として計上できる一方、税金もかかるため注意が必要です。また、どのような税金がかかるのかはケースバイケースのため、事前にどのようなルールなのかを把握しておかなくてはなりません。
ここでは、駐車場・駐輪場を運営する場合にかかる税金には、どのようなものがあるのか、また敷金・礼金・仲介手数料の税金についても解説します。

駐車場・駐輪場を運営する場合、以下のような税金がかかることがあります。
| ・固定資産税 ・都市計画税 ・所得税 ・償却資産税 ・消費税 ・個人事業税 |
ここから、それぞれの内容を解説します。
固定資産税は、駐車場経営においてもっとも重要な税金の1つです。課税標準額が以下の免税点を超える場合に課税されます。
| ・土地:30万円 ・家屋:20万円 |
通常、税率は1.4%ですが、駐車場の場合は住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地と比べて6倍の税額になることがあります。例えば、固定資産税評価額が1,500万円の駐車場の場合、固定資産税は21万円です。
ただし、アパートと一体利用と認められる駐車場の場合、税評価額が1/6に軽減される可能性があります。さらに、駐車場の形態によっても税額が変わり、舗装のない月極駐車場とアスファルト舗装された月極駐車場では計算方法が異なるため注意しなくてはなりません。
都市計画税とは、市街化区域内の土地所有者に課される税金で、固定資産税あわせて徴収されます。駐車場・駐輪場が都市計画区域内の市街化区域に位置している場合、課税対象で、税率は通常0.3%です。
固定資産税が免除される土地や家屋に対しては、都市計画税も課税されません。例えば、固定資産税評価額が1,500万円の駐車場の場合、都市計画税は4万5,000円です。
都市計画税も固定資産税と同様に、住宅用地の特例が適用されないため、駐車場経営では高額になる傾向がみられます。ただし、自治体によっては駐車場や駐輪場の設置を促進するために、固定資産税と都市計画税の減免措置を設けている場合もあるため注意が必要です。
駐車場経営で得た収入は、所得税の対象です。所得区分は、経営形態や規模によって不動産所得、事業所得、または雑所得に分類されます。例えば、50台以上の駐車場を運営している場合は事業所得とみなされる可能性が高いでしょう。所得税の税率は5%〜45%で、所得金額に応じて変動します。
サラリーマンが副業として駐車場経営を行う場合、年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。駐輪場経営の場合も同様の税金が課されますが、自治体によっては駐輪場設置の助成金制度がある場合も散見されます。
償却資産税とは、駐車場や駐輪場の設備に対して課税される税金です。取得価額が10万円以上の設備が課税対象です。課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
税率は通常1.4%で、計算方法は「償却資産税評価額×1.4%」です。対象となる償却資産は、アスファルト舗装、精算機、フェンス、照明設備、防犯カメラなどが挙げられます。例えば、総額500万円の設備投資を行った場合、初年度の償却資産税は約7万円です。
また、中小企業者等が取得した一定の機械装置等は、3年間課税標準を2分の1とする特例措置があります。駐車場・駐輪場の経営者は、毎年1月31日までに償却資産の申告を行う必要があり、適切な管理と申告を怠ると追徴課税のリスクがあるため注意しなくてはなりません。
駐車場も駐輪場も、整備された施設として貸し出される場合は原則として消費税の課税対象です。消費税は、駐車場・駐輪場の利用に対して課税される税金で、現在の税率は10%です。
ただし、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税の納税義務が免除されます。なお、インボイス制度の影響により、免税事業者であってもインボイス発行事業者として登録するかどうかの判断が必要です。
駐車場の形態によっても課税の有無が異なり、整備されていない青空駐車場や、契約期間が1か月以上の単なる土地の貸し付けは課税されません。つまり、単に土地を貸す場合は非課税取引です。
また、賃貸住宅に付属する駐車場で、一定の条件を満たす場合も課税されません。例えば、月額10,000円の駐車場利用料の場合、消費税込みで11,000円です。したがって駐輪場・駐輪場の経営者は、利用者の利便性を考慮しつつ、消費税の転嫁を適切に行う必要があります。
インボイス制度の詳細は、以下の記事をご参照ください。
インボイス制度が中小企業・個人事業主に与える影響とは?税理士に依頼するべき理由を解説
個人事業税は、個人事業主に課せられる税金で、駐車場・駐輪場経営者も対象です。収容台数10台以上の駐車場が課税対象です。290万円の事業主控除が適用されるため、小規模な駐車場経営では課税されないこともあります。
駐車場経営の場合、通常の税率は5%で、計算方法は「(所得-各種控除)×5%」です。例えば、年間の駐車場経営所得が500万円で、各種控除後の課税所得が400万円の場合、個人事業税は20万円です。
また、駐車場・駐輪場経営を法人化した場合は、法人事業税が課税されます。個人事業税は都道府県税のため、地域によって若干の違いがあるため、事前に確認しておきましょう。事業規模の拡大にともない、個人事業税の負担が増加する場合は、法人化を検討することも1つの選択肢です。

駐車場・駐輪場の経営形態によっては、敷金や礼金、仲介手数料が発生することがあります。ここからは、これらの税金の取り扱いについて解説します。
駐車場や駐輪場の敷金(保証金とも呼ばれる)は、通常であれば月額使用料の1~2か月分が相場です。契約時にオーナーに預けるお金で、以下の場合に使用されます。
| ・使用料の支払いが滞った場合 ・設備を破損させてしまった場合 |
問題なく使用していれば、解約時に全額返金されるのが一般的です。ただし、以下の点には注意しなくてはなりません。
| ・契約期間内の解約で返金されないケースがある ・保証金償却が設定されている場合、一部のみ返金される ・敷金・保証金には消費税はかからない |
駐車場・駐輪場の礼金は、オーナーへの謝礼金として支払われますが、必要ない場合も多いでしょう。礼金が必要なケースは、以下のとおりです。
| ・立地が良い駐車場 ・人気が高く空きがすぐに埋まる駐車場 ・月額使用料が相場より安い駐車場 |
礼金の相場は月額使用料の1~2か月分で、返金されません。また、礼金は消費税の課税対象外です。
仲介手数料は、不動産会社が提供するサービスへの対価であるため、消費税の課税対象です。以下の点に注意しなくてはなりません。
| ・仲介手数料には10%の消費税が課される ・土地や個人の居住用物件の売却は非課税だが、仲介手数料自体は課税対象 ・仲介手数料の上限額は法律で定められており、取引金額によって異なる |
400万円を超える取引の場合、以下の速算式で計算します。
| 仲介手数料の上限額(税別)=取引金額×3%+6万円 |
この金額に10%の消費税が加算されます。仲介手数料を計算する際は、税込み総額ではなく税抜き価格を使用することが重要です。土地(非課税)と建物(課税)が混在する取引の場合は、特に注意しましょう。

駐車場・駐輪場を運営する際にかかる主な税金は、固定資産税、都市計画税、所得税、償却資産税、消費税、個人事業税などです。特に、固定資産税や都市計画税は、住宅用地の特例が適用されず、税額が高くなる場合があります。また、消費税は課税対象となるケースと非課税のケースがあり、経営形態によって異なります。
さらに、敷金・礼金・仲介手数料の扱いも異なり、敷金は非課税、礼金は課税対象外、仲介手数料は消費税が発生するため、正しい税務管理が不可欠です。そのため、駐車場・駐輪場の運営を検討する場合、税理士などの専門家への相談も視野に入れなくてはなりません。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。