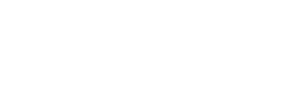
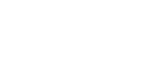
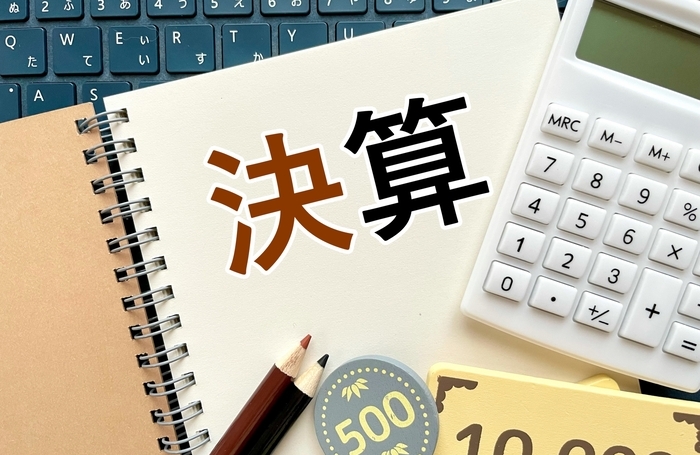
個人事業や法人を運営する場合、決済月を設定しなくてはなりません。決算月は事業の節目といえる大切な月であるため、慎重に決める必要があります。しかし、実際にはどのようなポイントに留意して決めるべきなのでしょうか。ここでは、決算月はいつがよいのか、多い月や決めるときのポイント、変更の可否などをご紹介します。
目次

そもそも決算月とは、どのような月間を指すのでしょうか。ここでは、決算月の定義と特徴をご紹介します。
決算月とは、企業の事業年度における最終月です。この月に、企業は一年間の収支を整理し、損益計算書や貸借対照表などの財務諸表を作成します。決算月は企業の財務活動を締めくくり、一年間の経営成績と財政状態を明らかにする重要な時期です。
決算月には、通常の業務に加えて決算関連の作業が発生するため、企業にとって業務負荷が高くなる点が特徴です。例えば決算残高の確定、消費税と法人税の申告および納付、決算書の作成などの業務が発生します。
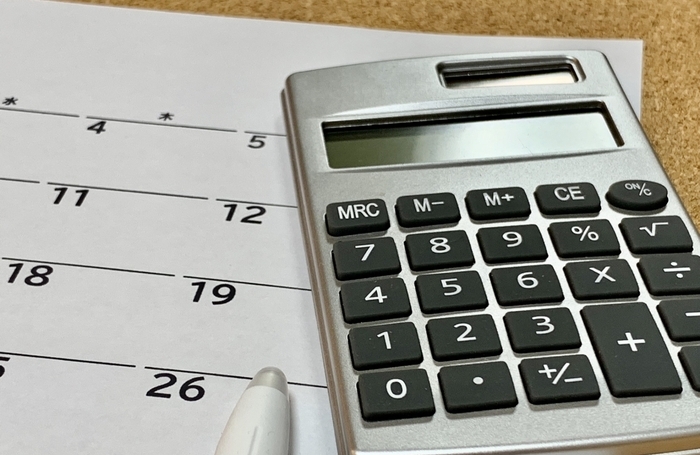
法人が会社を設立したり、個人事業主が起業したりする場合、決算月を決めておかなくてはなりません。ここでは決算月はいつがよいのか、個人事業主と法人の違いや、よく選ばれる月をご紹介します。
個人事業主の決算月は12月と法律で定められており、変更できません。1月1日から12月31日までが事業年度です。
一方、法人の場合は決算月を自由に設定できます。1年以内の任意の期間を事業年度として定めることが可能です。
日本企業の決算月として最も多いのは3月です。国税庁の統計によると、全法人のうち約18%が3月決算を採用しています。特に、資本金1億円以上の大企業では、50%以上が3月決算となっているのが現状です。
3月決算が多い理由としては、以下が挙げられます。
| ・官公庁の年度と一致する ・新卒採用や人事異動のサイクルに合わせやすい ・税制改正が4月から施行されることが多い |
3月以外に選ばれることが多い決算月は、9月や12月です。9月は繁忙期を避けやすく、12月は海外企業と決算時期を合わせやすいのがメリットです。

決算月を決めるときには、以下4つのポイントに留意しなくてはなりません。
| ・自社の繁忙期を避ける ・資金繰りに余裕がある時期を選ぶ ・業界の慣習や取引先との関係を考慮する ・公認会計士や税理士の繁忙期を避ける |
以下で、それぞれの内容を確認しておきましょう。
決算月は自社の繁忙期を避けて設定することが重要です。決算期には通常業務に加えて、決算書の作成や税務申告、株主総会の開催など多くの追加業務が発生します。繁忙期と決算期が重なると、本業に支障をきたす可能性があるでしょう。
また、決算業務は決算日から2か月程度続くため、その期間に十分な時間が取れるかも考慮しなくてはなりません。繁忙期を避けることで、決算業務に集中でき、ミスも防げる点がメリットです。理想的には、繁忙期から最も遠い月を決算月にすることで、年間を通じて効率的な業務運営を実現できます。
決算日から2か月以内に法人税や消費税などの納付が必要となるため、資金繰りへの影響を考慮することも重要です。手元にキャッシュが潤沢にある時期を決算月にすることで、資金繰りの不安を抑えられます。
特に注意すべきポイントは、以下のとおりです。
| ・大口の支払いや仕入れが集中する時期は避ける ・従業員へのボーナス支給時期と重ならないようにする ・売上のピークが決算月にならないよう調整する |
資金に余裕がある時期を決算月にすることで、安定した経営が可能です。
業界の慣習や主要取引先の決算月を考慮することも重要です。例えば、以下のような点に注意しましょう。
| ・国内企業との取引が多い場合は3月決算が一般的 ・海外企業との取引が多い場合は12月決算が適している ・公共事業に関わる企業は官公庁の会計年度に合わせて3月決算が多い |
取引先と決算月を合わせることで、複数のメリットが得られます。
まず決算処理が容易になり、業務効率が向上する点がメリットです。次に、同じ期間での業績比較が可能となるため、より正確な分析や評価が行えるようになります。さらに、海外子会社がある場合は、連結決算の作業がよりスムーズに進行するというメリットも得られます。
ただし、単に業界の慣習に従うだけでなく、自社の特性や状況を十分に考慮して決算月を決定することが重要です。各企業の独自の事情や戦略に基づいて、最適な決算月を選択することが、長期的な企業の成功につながるでしょう。
決算月を選ぶ際には、公認会計士や税理士の繁忙期を避けることが重要なポイントです。彼らの繁忙期は主に12月から5月、特に3月決算企業が多い4月から5月が最も混雑します。この時期を避けることで、より迅速で丁寧な対応、コスト削減、質の高いサービスを受けられる可能性が高まるでしょう。
またスムーズな連携により、決算や税務申告の作業が効率的に進められる点もメリットです。ただし、四半期決算の時期や業界特有の繁忙期も考慮する必要があります。理想的には、専門家の繁忙期を避けつつ、自社の業務サイクルとも調和する決算月を選ぶことが望ましいです。より効果的な会計・税務サービスを受けられる可能性が高まります。

法人の設立や個人事業の開業後などに、決算月を変更することは可能なのでしょうか。ここでは、決算月の変更可否について解説します。
決算月は企業が自由に設定でき、後から変更することも可能です。ただし「個人事業主と法人の決算月の違い」の項目で説明したとおり、個人事業主の場合は12月と決まっており変更できません。
決算月を変更することによって、以下のメリットが得られます。
| ・節税効果が期待できる ・資金繰りの調整が可能 ・役員報酬変更のタイミングを調整できる ・繁忙期を避けて決算業務を行える |
以下、でそれぞれの内容を解説します。
決算月の変更により、利益の計上時期を調整することで節税効果が得られる可能性があります。例えば、多額の利益が見込まれる月の前に決算を迎えることで、その利益に対する課税を翌期に繰り延べることが可能です。税負担を軽減したり、節税対策を講じる時間を確保したりする効果が期待できます。
決算月を変更することで、法人税の納付時期を調整し、資金繰りを改善できる場合もあります。例えば、売掛金の回収時期に合わせて決算月を設定することで、納税資金の確保がしやすくなるでしょう。季節性のある事業や大型案件を扱う企業にとって、有効な戦略となり得ます。
役員報酬は通常、事業年度開始から3か月以内に変更しなくてはなりません。決算月を変更することで、役員報酬の変更時期を前倒しすることが可能です。経営状況の変化に応じて柔軟に役員報酬を調整できるようになります。
決算月を変更することで、会社の繁忙期を避けて決算業務を行うことも可能です。決算業務に十分な時間と労力を割けるため、より正確で効率的な決算処理が行えます。また、従業員の負担軽減にもつながり、業務効率の向上が期待できるでしょう。
決算月を変更する場合、以下4つの点に注意しましょう。
| ・短期間での決算処理や納税対応が必要になる ・税金の計算に調整が必要になる場合がある ・前年度との比較が複雑になる ・変更手続きに手間と時間がかかる |
ここからは、それぞれの内容をご紹介します。
決算月を変更すると、変更年度は12か月未満の変則的な事業年度となります。そのため、通常よりも短い期間で決算処理や税務申告を行う必要があり、業務負担が一時的に増加する可能性がある点に注意しなくてはなりません。
決算期変更に伴い、減価償却費の計算や中小法人の軽減税率適用など、さまざまな税務上の調整が必要になることがあります。12か月未満の事業年度では、これらの計算が通常と異なるため注意が必要です。
決算月を変更すると、変更前後の事業年度の長さが異なるため、単純に前年度との財務データの比較ができなくなります。業績分析や経営判断を行う際には、この点に留意し、適切な調整を行いましょう。
決算月の変更には、株主総会の開催、定款変更、税務署への届出など、複数の手続きが必要です。これらの手続きには一定の時間と労力がかかるため、変更を検討する際にはこのコストも考慮に入れる必要があります。
以上の点を踏まえ、決算月の変更は自社の状況や目的に応じて慎重に検討することが重要です。メリットとデメリットを十分に比較検討し、税理士など専門家のアドバイスも得ながら、最適な決定を行うことが望ましいでしょう。
ここからは、決算月の変更方法を、ステップごとにご紹介します。
まず、株主総会を開催する必要があります。定款変更のための特別決議が必要なためです。決算月を変更するためには、議決権の3分の2以上の賛成が求められます。
株主総会で、決算月変更の賛成を得られれば、事業年度に関する記載を変更します。
次に、管轄の税務署へ「異動届出書」を提出しましょう。このとき、株主総会議事録のコピーを添付する必要があります。
税務署以外に、都道府県税事務所、市区町村への届出も必要です。また、主要取引先や金融機関への連絡も忘れず行いましょう。
決算月の変更は、企業の経営戦略や業務効率化に有効な手段となる可能性があるが、手続きの煩雑さや短期間での決算対応など、デメリットもあります。自社の状況を十分に検討したうえで、変更の是非を判断することが重要です。

決算月は、企業の事業年度を締めくくる重要な月で、業務効率や資金繰りに影響を与えます。法人は自由に設定可能で、繁忙期や税理士の繁忙期を避け、資金に余裕がある時期を選ぶことが推奨されます。特に多いのは3月で、税制や官公庁の年度に合わせる利点があります。決算月の変更も可能で、節税や資金繰り改善に寄与しますが、短期間での決算対応や手続きが必要です。税理士など専門家の助言を受けつつ、自社の状況に応じて慎重に決定しましょう。
税理士を探す際には、税理士紹介ドットコムの活用がおすすめです。手数料なども一切不要で、北は北海道から南は沖縄まで、全国ご希望のエリアで税理士をご紹介することが可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。